亡くなった人を悪く言わないという文化
日本人には、亡くなった人を悪く言わないという美徳があります。これは、仏教の「成仏思想」や神道の「鎮魂」の考えに基づいたものであり、同時に、他者の悲しみに寄り添うやさしさの表れでもあります。
しかしそのやさしさは、ときに「検証を止める力」として働くことがあります。感情的な敬意が、社会的な問いを封じてしまう――その矛盾を、私たちはどのように受け止めればよいのでしょうか。
安倍元首相の死後に見えた「沈黙の壁」
安倍晋三元首相の死後、日本社会では「偉大な政治家」「日本を取り戻したリーダー」という言葉が繰り返されました。一方で、政治資金の不透明さや派閥運営の問題、外交の成果など――本来、冷静に検証すべきテーマは、今もなお語りにくい空気に包まれています。
「死者に鞭打つな」という感情的な美徳が、「行為の検証」を避ける口実になってはいないでしょうか。この沈黙は、敬意の形を取りながら、「問いを恐れる社会」を作り出しているようにも見えます。
「物語化」される政治と外交
安倍氏の政治スタイルや言葉は、今も多くの政治家に受け継がれています。たとえば、高市早苗首相の所信表明演説にあった「世界の真ん中で咲き誇る日本外交」という言葉。それは、安倍外交を「誇り」として継承するメッセージにも聞こえます。
しかし、そもそも日本は本当に「世界の真ん中」にいたのでしょうか。そして、その「世界」とは、誰の視点によるものだったのでしょうか。
外交が「誇り」や「存在感」といった情緒的な言葉で語られるとき、実際の成果や国際的立ち位置の検証は、後回しにされがちです。政治が「物語」として美化されるとき、事実の再評価は難しくなります。
「世界の真ん中」とは誰にとっての中心か
米国との同盟を軸にした秩序を「世界の中心」とする見方があります。しかし、その“中心”は普遍的な価値ではなく、地政学的・歴史的な構築物にすぎません。
実際、米国の外交や軍事政策は、「民主主義の推進」や「世界の安定」を掲げつつ、中東やアジアでの介入、経済的覇権など、多くの矛盾を内包しています。その現実を見れば、「米国と歩調を合わせる=正義」、「その同盟の中での存在感=成功」とは、単純に言い切れないはずです。
それでも日本では、外交が“理念”よりも“誇り”で語られ、感情的な物語が事実の検証を覆い隠してしまうのです。
検証することは、攻撃ではない
日本では「批判」は「攻撃」と混同され、「検証」は「不敬」と見なされる傾向があります。しかし、本来の民主主義における検証とは、社会が成熟するための再評価のプロセスです。
人物の功績と問題を、同じテーブルの上で見つめること。美化と否定のあいだにある“中間のまなざし”を持つこと。それこそが、知的で誠実な社会のあり方ではないでしょうか。
やさしさと知性の両立を
「死者を悪く言わない」こと。
「真実を語る」こと。
この二つをどう両立させるか――。
それは、単なる政治や倫理の問題ではなく、やさしさと知性をどう共存させるかという、日本社会への問いです。敬意を持ちながらも、問いを手放さない。それが、私たちが「沈黙から抜け出す」ための第一歩なのだと思います。□
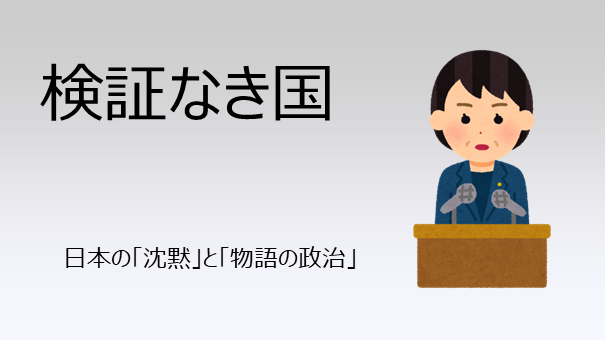

コメント