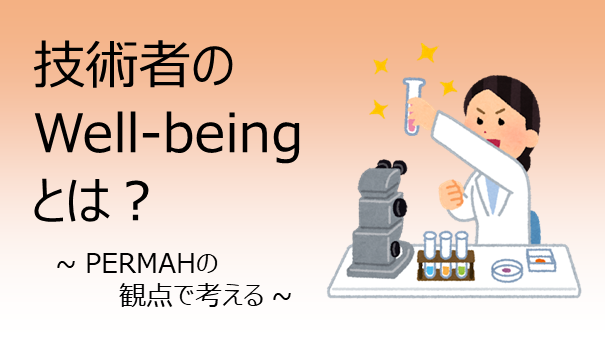 技術者倫理
技術者倫理 技術者のWell-beingとは? ~PERMAHの観点で考える~
札野教授が提唱する技術者倫理教育は、Professional としての技術者の在り方を問うものであり、Well-beingを目的とします。ここでは主体的幸福度を測る指標として、PERMAH理論を紹介します。この観点によって一見バラバラな技術者のWell-beingが明確になり、技術系部署で講じるべき対策が見えてきます。
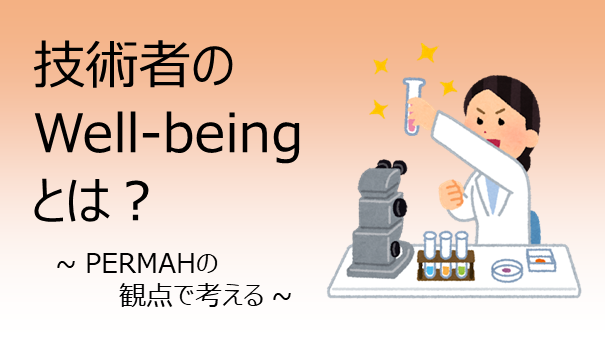 技術者倫理
技術者倫理 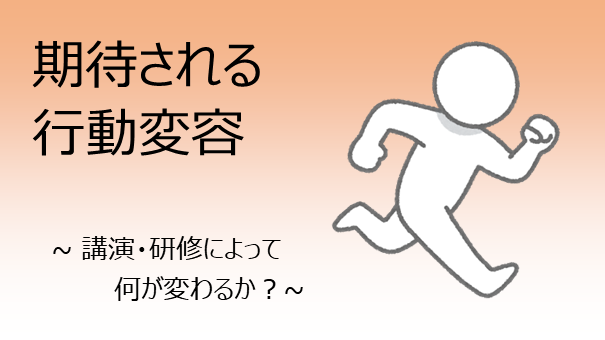 技術者倫理
技術者倫理 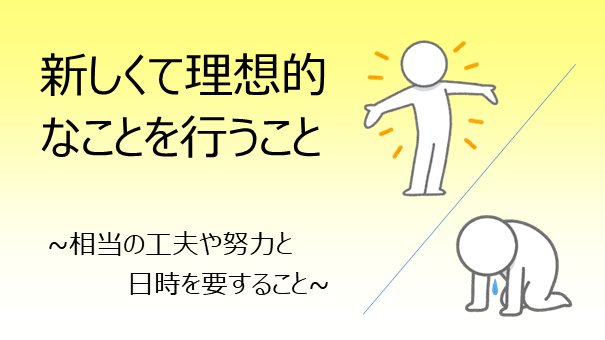 今ここをよく生きよう
今ここをよく生きよう 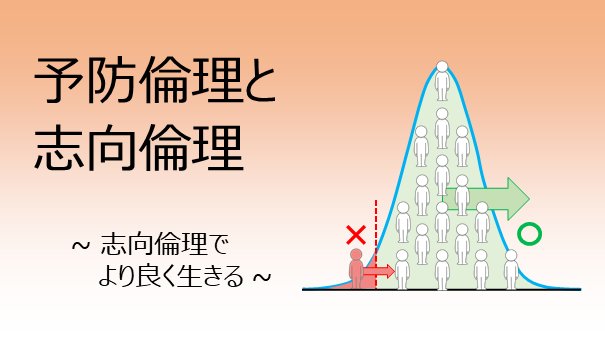 技術者倫理
技術者倫理 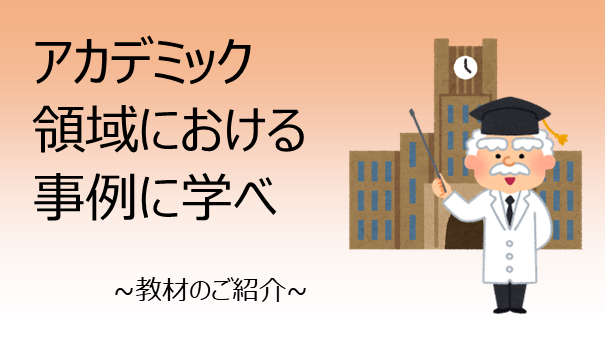 技術者倫理
技術者倫理 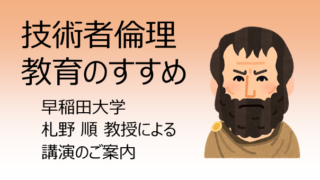 技術者倫理
技術者倫理 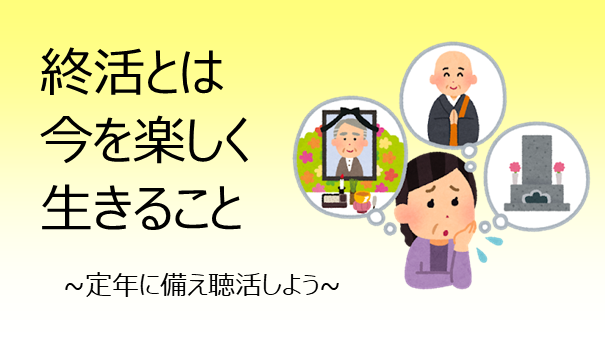 今ここをよく生きよう
今ここをよく生きよう  今ここをよく生きよう
今ここをよく生きよう  今ここをよく生きよう
今ここをよく生きよう 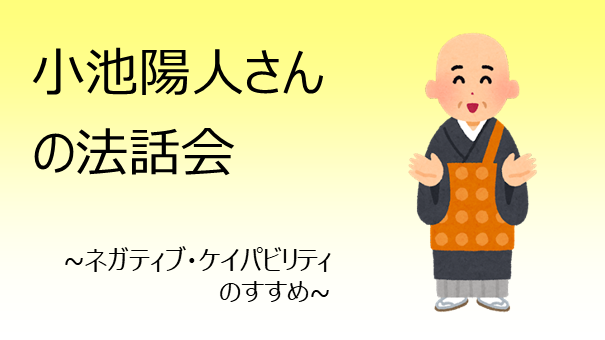 今ここをよく生きよう
今ここをよく生きよう  今ここをよく生きよう
今ここをよく生きよう 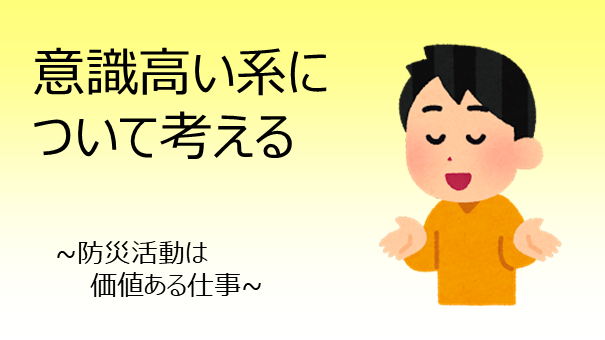 今ここをよく生きよう
今ここをよく生きよう  今ここをよく生きよう
今ここをよく生きよう 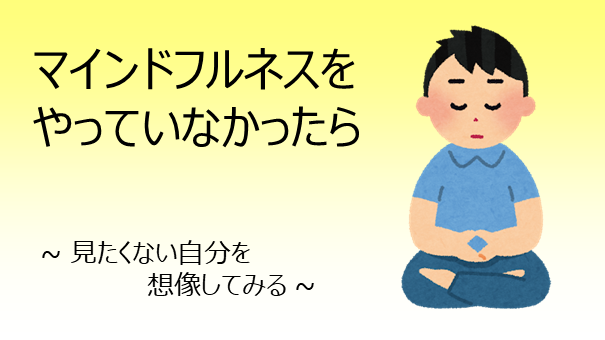 今ここをよく生きよう
今ここをよく生きよう 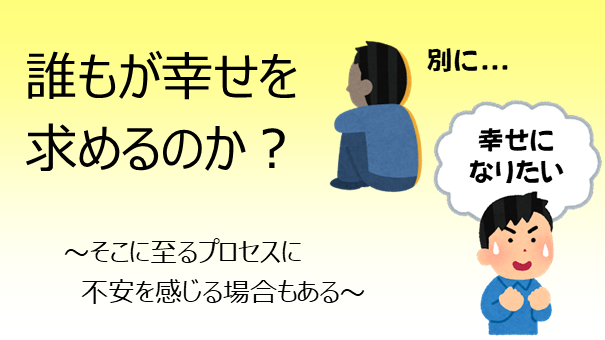 今ここをよく生きよう
今ここをよく生きよう