キャリアコンサルタント資格を取得し、希望に燃えていたはずなのに「”現場”から声がかからない/相談者が来ない/制度が上手く動かない…」そんな思いを抱いたことはありませんか?
私はここで「キャリアコンサルタント資格では食えないよ」という、”よくある話” を改めて主張したい訳ではありません。
受験生の皆さん、有資格者の皆さん、「この資格をどう活かすか?」という ”自分本位の目線” を180度転換しないと、キャリアカウンセリングを生業にすることも、企業内キャリコンとして食って行くことも容易でないと、お伝えしたいのです。
面接試験における刷り込み
キャリアコンサルタント面接試験における「資格を取ったらどう活かしますか?」は、唯一答えを準備できる質問。どう答えたら試験官に伝わるかについては、先のコラムに書きました。
しかし、もっと大切なことは、この質問の ”呪縛” から解かれ、相談者(=お客様)目線へ切替えることです。
これを書いてから一年、私は粛々と相談者目線/お客様目線への転換を図ってきました。以下に、その変遷をお伝えします。
試験問題のように正解がある訳ではない
私は、論述試験対策を徹底的にやり、苦手な面接試験を補って合格したクチです。前職での仕事柄、書くことは得意だったのです。今思えば稚拙な回答でしたが、その後2年半、受験生へのアドバイスをするうち、対応策は洗練されたように思います。皆さん、私の現役時より遥かに高い点数を取っておられました(笑)。
そんなことをするうち、私の脳内には、論述/ロープレのパターンが刷り込まれていきました。しかしその後、実際のカウンセリングをさせていただく中で気付いたのは…
- 初めから、来談目的を明確に語る人なんて居ない
- 何に悩んでいるか分からないで来る人も居る
- 具体的な経験なんて、ベラベラしゃべらない(しゃべり過ぎの人も居ます)
- 正解なんて、本当にない
ということです。
昨今、私はビジネスパートナーとして生成AIを活用しています。試しに「論述試験の逐語録」読ませ、主訴を書かせてみました。試験問題には著作権があるので、詳細は公開できませんが、生成AIは洗練された素晴らしい文章を返してくれますよ。もちろん、プロンプト(命令文)には、それなりの工夫が必要ですが… 当たり前ですが、試験問題は、あくまで試験問題なのです。
キャリコン初心者が直面する課題
試験は試験
「実際の面談は、試験とは違う…」資格取得後、面談の機会に恵まれた方は、直ぐに気付きます。「これじゃあ、実際の面談なんて出来ない!」と思った人が行く先は、ロープレ会です。かく言う私もロープレ会に2年半参加しました。そこでの学びは本当に楽しく、充実したものとなりました。沢山のことを学び、その内容は拙著に記しました(「Well-beingなキャリアとは何か?」Amazon 電子書籍)。しかし相談者はキャリコンもしくは受験生。「お作法をわきまえており、内省力の高い人たち」です。いくらロープレをやっても、現場の相談者とはかけ離れているのです。
資格取得の沼
なお、その間も社内で相談窓口を開設していましたが、利用者はごく僅かでした。キャリコン仲間も社内で奮闘していましたが、思ったような仕事が出来ている人はごく僅か。そんな中には「次は技能士2級を!」と次の資格に向かう方も少なくありませんでした。「国キャリの上位の2級技能士を取らないと、本当のキャリコンとは認められない!」などという話が、まことしやかに語られていました。私はそれを見て「資格取得の沼では?」と思っていました。
経験を積める場所が限定
考えてみれば、資格を取ればすぐできる仕事なんて、どこにもありません。士業の方は資格取得後、〇〇事務所に所属し、先輩に付きながら仕事を覚えていきます。キャリコンが士業と違うのは、修行を積む行政機関、教育機関、事務所が極めて限られていることです。私も幾つか、その求人に応募しましたが、求められるのは即戦力であり、面談の経験値です。初心者お断り。当然のごとく、書類選考で落とされました。面接まで行ったときは、「貴方の経歴なら、他の道に行った方が良い」と諭されました。実質、説教でしたね(笑)。キャリコン初心者が経験を積める場は圧倒的に少ないのです。
企業内キャリアコンサルタントを目指す上での壁
キャリアコンサルタント資格取得者のうち、企業内で働く方は約4割と言われています。私の同期のキャリコンにも、企業で働く仲間が多数おられます。既に人事やキャリア関連部署に所属しており、資格取得後、即キャリア関係の仕事に活かせる方もいますが、実は少数。多くの方は人事に所属していてもキャリア担当ではなかったり、人事とは全く関係の無いお仕事をされているいるのです。
皆さん、実技試験において「資格を取ったら(関連部署に異動して/新しく部署を立ち上げて)セルフキャリアドックを運営したい」と ”宣誓” するのですが、その道は険しい。当初の思いが強かった人ほど、その現実に打ちのめされ、資格更新さえ諦めておられる方もいるようです。

でも、あんなに苦労して取得した資格です。「他人のキャリアを支援する以前に、キャリコンとしての自分のキャリアをどうにかしなくては!」と思うのは自然なことです。しかし「キャリコンとしての…」というところが、かなりの曲者。我々は養成講座や所属団体から「キャリコンとしての生き方、在り方」を叩き込まれています。それはとても崇高なものであり、それを貫こうとする方は指導者を目指すようです。
「自分のキャリアにもがく」が故のプロダクトアウト思考
私も当初は企業内キャリコンを目指していました。受験生の頃から、研究開発部署でキャリア支援の仕事を始めており、資格取得後は改革心に満ち溢れていました。しかしキャリア面談の道筋はつけたものの、全社展開にはほど遠く、しがらみの無い社外に飛び出したのです。経営陣の理解を得て、会社の取組みとして立上げ、継続していくのは容易ではないのです。
退職後、個人事業主となった私は、相変わらず「資格を活かす」ことばかりを考えていました。集客のためのホームページには、「こんなことできます。あんなことできます。どうぞ声かけて下さい」と書いてある。そんな頃、私は一つのことに気付きました。
あっ... 自分の資格を活かすことばかり考えている自分は、完全に”プロダクトアウト思考”になっている。 大事なのは”マーケットイン”だと、あれほど前職で主張していたのに...
私の前職は自動車部品会社の研究開発職。エンジン車の部品製造で大きくなった会社ですが、「高品質のものを作れば売れる」というプロダクトアウト的発想は過去のもの。お客様が本当に欲しいもの、今後欲するであろうものを提供する、マーケットイン思考への切替えが求められていました。研究企画部署に居た私は、研究者に対して思考の転換を促していましたが、同じ思考に陥っていたのです。
その頃、私のホームページを見た人事系コンサルの方には、「貴方、ほんとに自分が大好きな人ね…それはとても大事な事だけど、これじゃあ、どんな問題を解決してくれるのか、見た人が全く分からない」と言われました。前職で叶えることができなかったキャリアコンサルティングに対する執着するあまり、「お客様のどんな問題を解決したいのか?」が完全に欠落していたのです。
どんな問題を解決できるのか?
今思えば、当時は「表面的な問題解決思考はダメ」という、カウンセリングマインドに心酔し過ぎていました。そのため「どんな問題を解決できるか?」なんて「書けないし、書かない」のが ”正義” だと思っていたのです。
もちろん、ロジャーズの「自己成長論に基づくカウンセリング」は今でも大好きです。「人は自らの可能性の実現に向けて、自らを発展させようとする傾向を持っている(実現傾向)」は大乗仏教に通じる考え方だと思うのです。
しかし、私のお客様である企業人は「問題解決してナンボ」と考えます。「どんな課題を解決してくれるのか?」がイメージできなければ、彼らから受注など出来ません。
キャリアカウンセリングを生業にしようしている方へ
前述したように、キャリアカウンセリングを生業にするのは、容易ではありません。”実際の相談者”との面談機会を得るのは容易ではないからです。でも、その志は大切にして欲しいと思います。なぜなら、貴方自身が歩んできたキャリアは唯一無二のものであり、貴方でなければできないキャリアカウンセリングがあると思うからです。
女性カウンセラーは、数々のライフイベントを乗り切ってきた、ご自身の経験を糧にして、活躍されている方が多いですね。私のような男性は叶わないな…とつくづく思います。その一方で、キャリコン受験生仲間には、セカンドキャリアへの足掛かりとして資格を取得された、オジサンもたくさんおられます。彼らが歩んできた企業人としての人生は唯一無二。若干頭が固いという傾向はあるものの、資格取得時に「聴く力」を身に付けてこられた方々なのです。十分なカウンセリング経験は無くても、後輩に何かを遺すことは出来ると思うのです。
もし、オジサンに限らず「カウンセリング経験は少ないのだけれど、自身の経験を活かして、カウンセリングをしたい」という方がおりましたら、ぜひご相談下さい。オンライン相談室にてお話しを聴かせていただきます。
私もターゲット層を拡げたり、絞ったりしながら、試行錯誤を繰り返しています。貴方が置かれている環境、貴方の強みを活かし、「相談者の問題解決を支援できる道」を一緒に探しましょう!
企業内キャリアコンサルティングで事を成したい方へ
私は、前職において、企業内キャリコンとして敗れ、しがらみのない社外に飛び出した人間です。「企業内コンサルティングで、事を成したい!」と、もがき苦しんでいる方が、直面する問題については、それなりに経験をしています。
もし、あなたが企業内キャリコンで、私と同じような悩みを抱えているのなら、ご連絡下さい。「貴社の問題解決」に向かうために何をすべきか? 一緒に考えさせて下さい!
↓その他キャリコン情報↓
↓コラムを書籍化 500円↓
↓ Xでもつぶやいています ↓
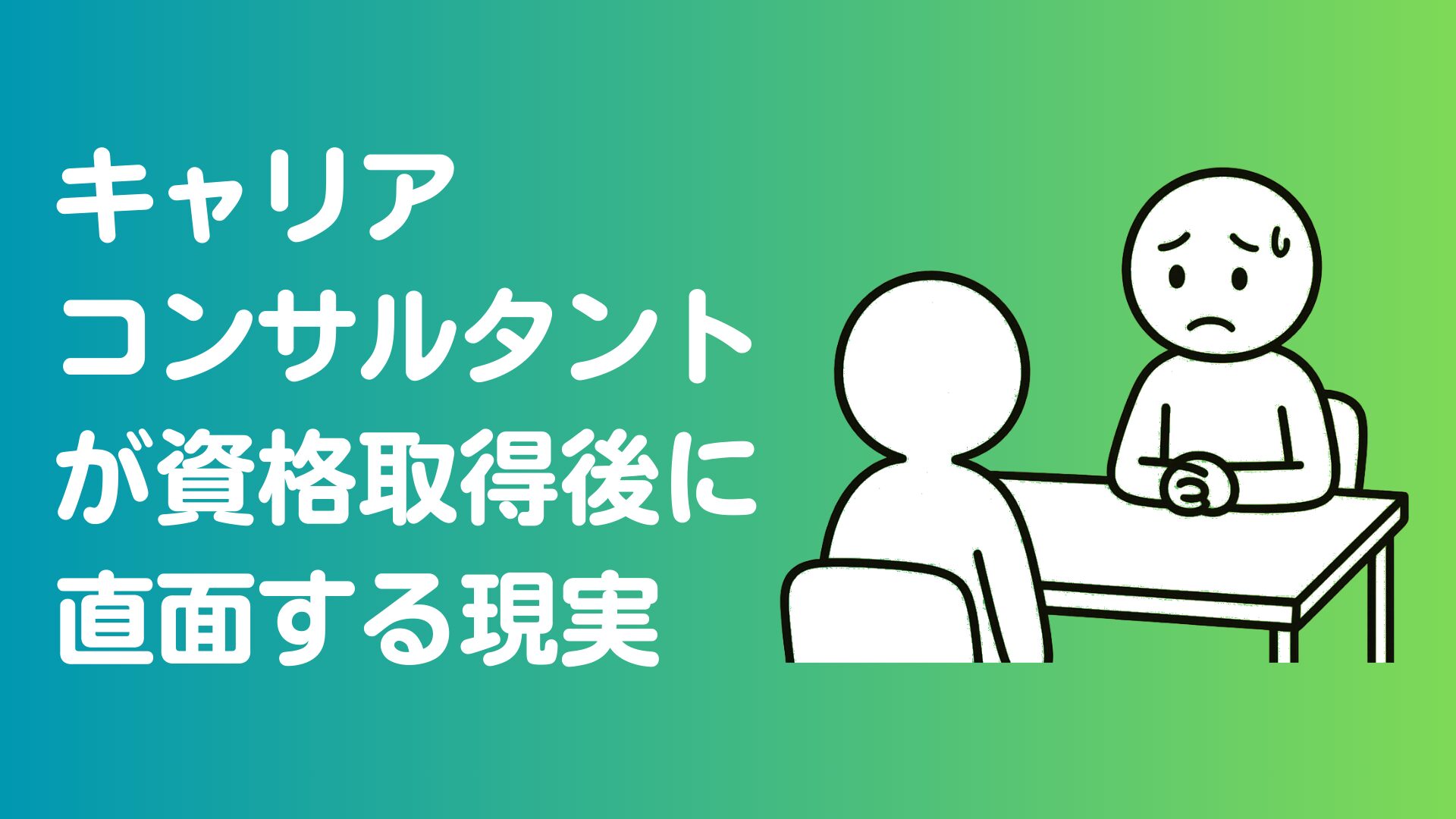



コメント
改めてマーケットイン思考の大切さを考えさせられました。ありがとうございますm(._.)m
キャリアコンサルタント取得後、プライベートで大きく広がってきている経験から、仕事で活かすだけが全てではないと感じています。
マネタイズに関しては考える余地ありですが、力になりたい方々へ、少しずつ力になれていることはモチベーションに繋がっています。
コメント有難うございます。
多くの人が自身のキャリアに悩む中で、資格取得に向かうのだと思います。ですから「自分の能力、資格を活かしたい!」と考えるのは、とても自然なことですね。
但し、多くの時間、費用をかけて資格を取ったのに、思うような仕事が出来ないと、思考が偏ってきてしまいますよね。
元々、他人の役に立ちたくて資格を取ろうとした人たちが多いので、「相手目線で考える」という、原点に返ればいいだけなんだと思います。