厚労省のお気に入り
厚生労働省の資料を読んでいると、「自律的キャリア」もしくは「キャリア自律」という表現が度々出てきますね。例えば「経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に関する研究会 中間とりまとめ」には、以下のような表現があります。
労働者が生涯にわたり充実した職業人生を送るためには、労働者が自身の将来のキャリアについて考え、主体的に能力開発に取り組み、必要に応じて内部・外部労働市場において自らの能力をより発揮できる仕事に移動していく「キャリア自律」に取り組むことが不可欠になっている。
なんかモヤモヤ…
はて? なんかモヤモヤする。
自律とは「他からの支配・制約などを受けずに、自分自身で立てた規範に従って行動すること(デジタル大辞泉)」であって、会社組織や社会情勢から大きな支配・制約を受けている、現代の仕事を考えるとき、この言葉の使い方は適切なのか?
労働市場の流動性を上げたいという、政府および経済界の思惑は分かります。「不可欠になっている」と状態を示し、”誰が”不可欠だと言っているのか、主語を曖昧にしたいのだと思いますが、かえって”上から目線”を感じてしまうのは私だけでしょうか?
私は前職で研究開発部門のキャリア教育を担当してきました。声高にキャリア自律の必要性を叫ぶと、「これまで理不尽とも言える会社都合に従ってきた。今更、自律的キャリアの時代だと?」と噛みつかれました。他律の”他”である会社側が、 社会情勢のせいにして、 ちょっと高飛車な感じで自律という言葉を使うと… そりゃあ、イラっとしますよね。「お前、時代の変化に先に気付いたのかもしれないが、そんなに偉ぶるなよ」と言われていたのだと、今なら思えます。
なぜよく使われるのか?
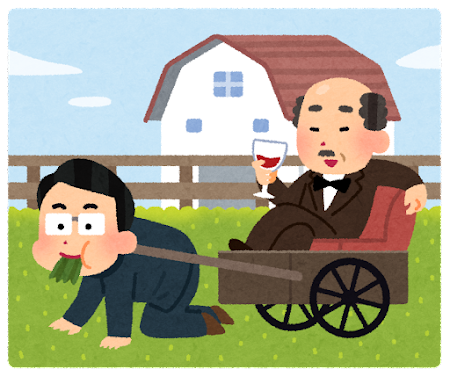
自律的キャリアという言葉を、 お役人がよく使うのは何故でしょうか? 従来のキャリアは従属的(力の強いものに依存し、言いなりになっている状態)な面が強かったと思います。けれど、そこまで言うと、”社畜”をイメージするのでキツ過ぎる。 だから他律と言い換え、その反対語として、自律という言葉を使ったのではないでしょうか? 自分で立て!という”自立”も同音だし。何だか前向き… 「失われた30年で苦労した労働者よ! 今こそ自ら立ち上がれ~!」みたいな感じですね。いや、自立が先にあって、「それだと命令っぽいから、自律にしようよ…」となったのかもしれません。
では現在、会社の中核を担う方々は自律していないのか? そこで就職氷河期世代の人たち(現在40~55歳)と話してみると、そもそも会社と言うシステムに対し従属的ではない。従属的だったのは私を含む、その上の世代だと思うのです。ひょっとして「自律的キャリア」を掲げ、従属的キャリアからの脱却を促そうとしている世代って、私より上の世代なのでは? 誤解を恐れずに言えば、「自分も従属的なキャリアを歩んできた。けれど、それではダメだと気が付いた。皆、立ち上がれ~」と叫んでいる… けれど現役世代は「自律? 何だか上から目線だね…」と思っているのではないでしょうか? 私のモヤモヤの正体は、この温度差だと思うのです。
どう呼ぶのが適当か?
私は、我々世代が従属的キャリアを歩んできたことを再認識することが必要だと思うのです。別に卑下する必要はありません。そういう時代に生きてきたのですから… その上で従来のキャリアを「受動的キャリア」、これからのキャリアを「主体的キャリア」と呼んだ方が良いと思うのです。「自ら律する」という”強く正しいイメージ”を押し付けられるよりも、いいのではないかと思うのです。「自ら動け!」と強制されて、自ら動く人は極めて少ないのですから、その言葉を聞いた人の心を動かしたいのであれば、言葉を変えるべきではないでしょうか?
最後に、ChatGPT先生に「自律的キャリア」に相当する英語表現を訊いてみました。
- Protean Career
- Boundaryless Career
- Self-directed Career/ Career Self-Management
プロティアンキャリアは、Identity と Adaptability の2軸で考えるから、自律だけではない。バウンダリーレスキャリアは、垣根を超えて働くキャリア。どれも根底にあるのは、”主体性”だと私は思います。□
↓その他キャリコン情報↓
↓コラムを書籍化 500円↓
↓ Xでもつぶやいています ↓
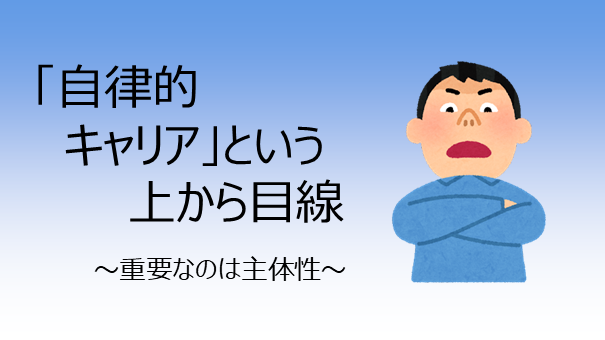



コメント