―― センサの感度を上げ、「自分を大切にする」練習
はじめに
技術者でも、ビジネス職でも、家族を支える立場でも――
私たちはつい、「後回しにされがちな自分」を抱えています。
忙しさの中で、
- しんどさ
- さみしさ
- 不安
- 小さな違和感
こうした“微弱な信号”は、ノイズに埋もれて見えなくなってしまうからです。
しかし、本当にしんどくなる前に気づける人は、メンタルの壊れ方がまったく違います。
これは技術者の方にも、非技術者の方にも共通する、とても大切な視点です。
なぜ「センサの感度」が大切なのか
技術の世界では、センサの感度が高いほど、
“異常の予兆”に早く気づけます。
人間の心も同じで、
強いストレスを感じる前には、かならず“弱い揺れ”があります。
- なんとなく集中できない
- 朝、起きづらくなってきた
- いつもより感情が乱れやすい
- 人に会うのが億劫になってきた
- 「頑張らないと」と思う回数が増えた
これらは、まだ壊れてはいないけれど、調整が必要なサインです。
医療につながるほど悪くなる前に気づければ、
多くの場合、時間も労力も少なく済みます。
自分のセンサを鈍らせてしまう「思考のクセ」
やりすぎてしまう努力
「もっと頑張らなきゃ」
「今の自分じゃダメだ」
「周りの期待に応えなきゃ」
こうした思いは、明るい側面では“成長の燃料”になります。
しかし、度が過ぎると 自分を追い込む圧力 に変わり、
結果として“本当のしんどさ”を隠してしまいます。
自縄自縛 ― 自分の言葉が自分を縛る
技術者の多くが、問題解決に真面目です。
だからこそ、
- 「やれない理由」の沼にはまる
- 出来ない自分を責める
- 完璧にやらねばと思い込む
といった「自縄自縛」に陥りやすいのです。
私は以前、その“縛り”の渦に長くいた人間です。
そこから抜け出す過程で、
自分への見立て・受容・調整の方法を数多く試し、数多く学びました。
その知見は、相談室で丁寧にお伝えできます。
(※自縄自縛についての詳しい記事は後述の関連記事へ)
“自分を大切にする”とは、甘やかすことではない
誤解されがちですが、
自分を大切にするとは 逃げること ではありません。
むしろ逆で、
- 状態を正確に把握する(見立て)
- 抱えている負荷を認める(受容)
- 必要な調整をする(行動)
という、高度な自己マネジメントです。
技術の世界に喩えれば、
「故障してから直す」のではなく
「予兆を早めに拾い、システムを長持ちさせる運用」に近いものです。
相談は、“壊れてから”では遅い
メンタルクリニックに通うほど悪くなる前に、
「少し気になる段階」で相談するほうが、
はるかに楽で、効果も大きい。
これは、私自身が相談を受け続けてきて確信していることですし、
多くのカウンセラーやコンサルタントも同じ思いを抱えています。
あなたがいま抱えている“小さな揺れ”は、
ちゃんと向き合えば、必ず整っていきます。
まとめ
- 小さな違和感は“心のセンサ”からの信号
- その感度が高いほど、しんどくなる前に調整できる
- 過度な努力・自己否定は、センサを鈍らせる
- 自己受容は“高度な自己マネジメント”
- 相談は、悪くなる前ほど効果的
あなたの心が少しでも「しんどい」と言うなら、
その声は大切に扱ってください。
関連記事(あわせて読みたい)
自分を大切にしようとしても、
気づかないうちに自分を責めてしまうことがあります。
そんなときに、まず立ち戻りたい視点が「自己受容」です。
- 自分を責めてしまうあなたへ ― まず“自己受容”から始めよう
自分を責め続けて苦しくなる仕組みを解説しています。
関連して読みたい記事
- 自縄自縛 ―自分で自分を縛らない
言葉や思考のクセが、自分を追い詰める仕組みを解説しています。 - 悩みはひとそれぞれ けれど同じような悩みを持っている人はたくさん居る
技術者特有の“悩みの共通項”について解説した記事です。
□
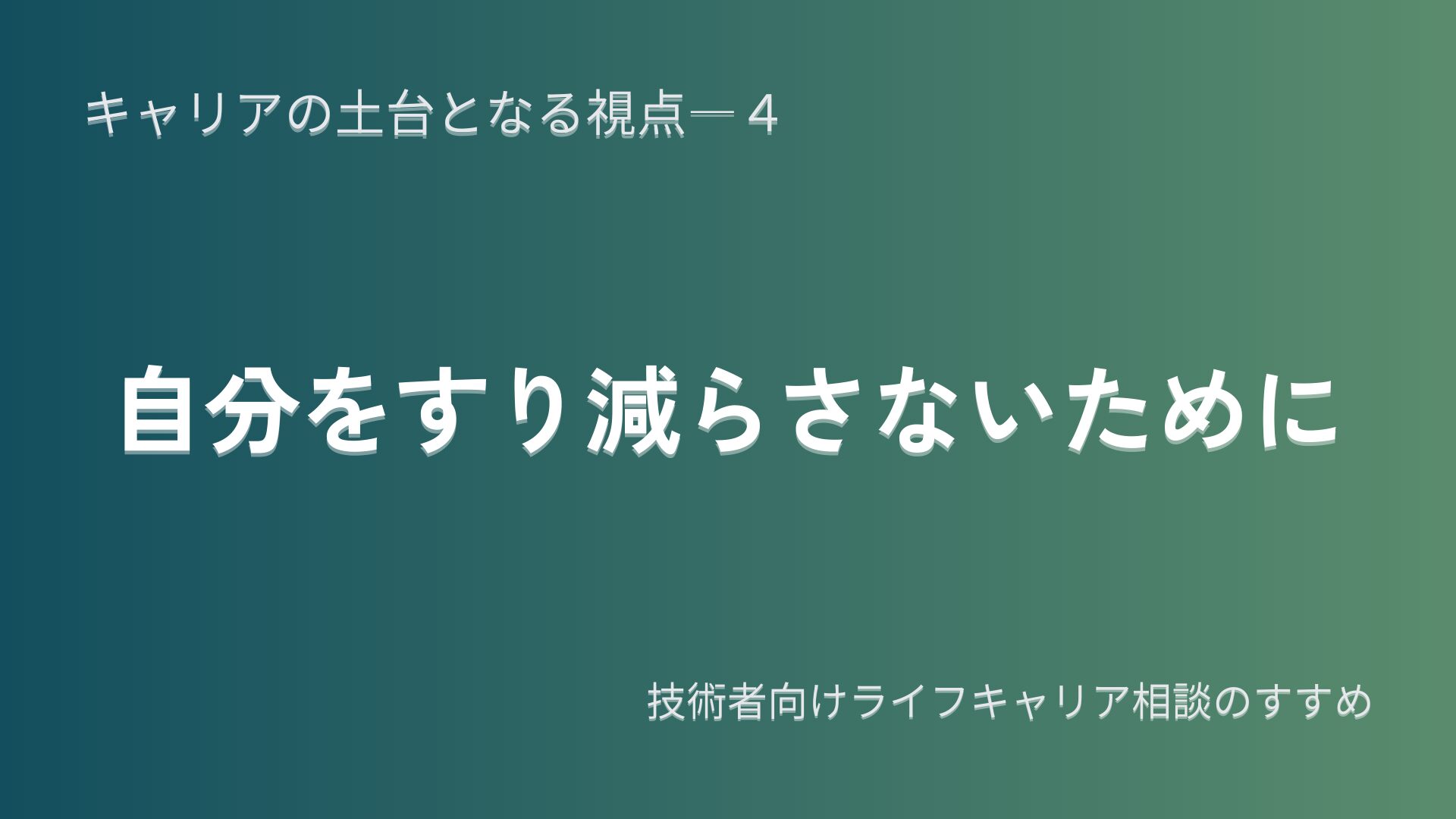
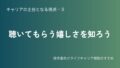
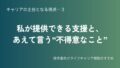
コメント