専門能力で生きてきた技術者の皆さん、昨今の転職エージェントのCMを見ていると、「積み上げてきた自身のキャリアが、外部からどう評価されるのか?」が気になりますよね。そこで「ポータブルスキル」とやらを評価してみると… あれあれ? 何だかおかしい…
「ポータブルスキル見える化」の動きと「専門性」
近年、「ポータブルスキルの見える化」が進み、厚生労働省も専用ツールを提示するなど、雇用の流動化に向けた取り組みが活発になっています。しかし、この仕組みを技術系専門職が使ってみると、ある違和感に気づきます。
“専門家としての価値が、まったく見えてこない”
設計・解析・実験・開発・品質・安全… 技術の本質を形づくっているスキルは、汎用的なスキルの枠組みでは測定しきれません。そのため、専門性の高いエンジニアほど「自分の価値が正しく表現されない」というジレンマを抱えがちです。
実際、ミドルシニアの技術者の中には、このモヤモヤを解消するために、技術士資格や大学院での学位取得に挑戦する人がいます。目に見える証明を得ようとする行動は、私自身、工学博士として理解できます。「社内で理解が得られなくとも、学会で評価されれば満足だ」という人もおられます。
しかし——資格や学位は 「すごい専門家」 であることを示すだけで、“どんな価値を提供できる人なのか” までは伝えてくれません。むしろ今の時代は、専門家こそ価値を翻訳して伝える力が求められているのではないでしょうか?
専門性が深いほど、価値は伝わりにくくなる
エンジニアとして長く経験を重ねるほど、成果やスキルは“暗黙知”として蓄積し、かえって言語化しづらくなります。
「できること」は多い だが「説明できること」は少ない
という状態になりがちです。
さらに、キャリアの後半になってくると、
- 若手の育成
- 顧客や関連部署との折衝
- 技術判断の説明
- 開発プロジェクト全体の舵取り
といった “伝える技術” が強く求められるようになります。ところが、この「説明する力」「価値を翻訳する力」は、専門教育の中ではほとんど扱われることがありません1。
キャリアコンサルタント業界も同じ課題を抱えている
実はこの問題、私がもう一つの軸としているキャリアコンサルタント業界にも当てはまります。
資格を持っている人は増えましたが、
「キャリアコンサルタントは何をする人なのか?」
が依然として社会に伝わっていません2。
理由は単純です。キャリア支援の価値が、支援対象者も、相談内容も幅広く、抽象化しすぎているため、伝えきれていないのです。比較的明確なのは、学校領域と就職支援領域のみ。厚労省がキャリコン増員の目的とした、企業領域での支援は曖昧なままです。結果、市場も拡大しにくくなっていると思われます。
つまり、
- 技術者 → 専門性の価値が伝わらない
- キャリアコンサルタント → 支援の価値が伝わらない
という、全く異なる2つの領域が、同じ「価値を翻訳できない」という壁にぶつかっていると感じています。
工学博士 × キャリアコンサルタントとして、私ができること
私は長年、技術者としてキャリアを歩み、博士として専門性を磨いてきました。その後、研究所の企画部員として、多くの技術者のキャリアを見てきました。そこで痛感するのは、「技術者は、もっと自身の価値を伝えることで、報われても良い人たちなのだ」ということです。
- 経験の棚卸し
- 専門知識の翻訳
- 課題解決力の言語化
- セカンドキャリアの方向性づくり
- 専門性を社会の言葉に置き換える作業
これらは、単なる「職務経歴書の書き方」や「転職ノウハウ」といった表面的な話ではありません。その人が何者で、何ができて、どんな価値を生み出せるのかを、本人と一緒に言語化していく作業です。技術者にとっても、キャリアコンサルタントにとっても、これから重要なのは “専門性を価値として翻訳する力” ではないでしょうか。
最後に──価値を言語化できる人が、これから強い
専門家とは、「専門性が高い人」ではなく、“専門性を分かる形にできる人” のことだと、最近強く感じます。資格や学位があっても、それだけでは価値は届きません。技術者であれ、キャリアコンサルタントであれ、求められているのは、価値を翻訳し、伝え、相手の意思決定に役立てる力。
この変化を丁寧に見つめ、私自身もまた「自分はどんな価値を提供できる人なのか」を言語化しながら、技術者のキャリア支援を続けていきたいと思います。□
- 昨今の大学・大学院教育では、これらの力を高めるためのカリキュラムが組まれていることも多くなってきました。また民間の研究所でも、提供価値を分かりやすく説明するための教育が行われています。 ↩︎
- 私もキャリアコンサルタントとして、「どんな領域の、誰に、どんな価値を届けられるのか?」を発信し続けています。 ↩︎
今の働き方を見つめ直したい方へ
現場を支える人材を育てたい企業へ
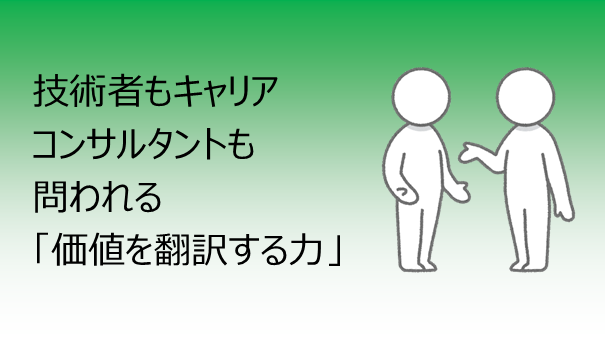


コメント